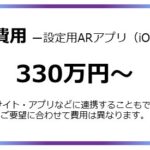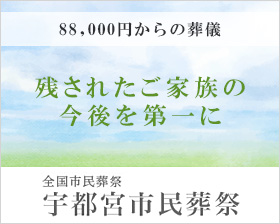目次
突然の喪主でも慌てずに。押さえておきたい葬儀の注意点
葬儀は突然準備がはじまります。
そんな葬儀においてもちろん主役は亡くなった方であることでしょう。葬儀は人生という長く苦しく、そして時に嬉しくも楽しかった時間の終幕です。
一人の人生にはその人の生という時間がぎゅっと凝縮され、死によって命に幕を下ろし、葬儀によって社会的にも幕を下ろすということができるでしょう。
そんな一人の人の旅立ちを見送る会こそが葬儀なのですが、誰かが準備をしなければ当然ながら葬儀をとり行うことはできません。
ちょっと違うかもしれないですが、飲み会を考えてみてください。飲み会には幹事がいて、皆の都合を確認して飲み会の予約から集金までこなしますよね。
葬儀も同じで、亡くなった人は自分の葬儀の主催(幹事)はできませんから、亡くなった人と特に親しい人が幹事役になって葬儀をとり行うことになります。
この幹事役こそが「喪主」です。
今回は一人の人の人生の終幕であり、旅立ちでもある葬儀において喪主を務める方の注意点についてお話しします。喪主は幹事のような存在。とても責任重大ですよ。
喪主って何?どんな人のこというの?
喪主はいわば葬儀の幹事のような役割を担います。
急に人が亡くなるという慌ただしい中、喪主を中心に葬儀は進み、喪主を中心に葬儀も進みます。
喪主は亡くなった人側の代表でもありますから、時に亡くなった人の言葉を代弁し、葬儀に参列してくれた人に代わって挨拶を申し上げます。
一般的なお祝い事などの会であれば、本人が挨拶をすることが基本ですよね。
例えばお誕生日会。誕生日を祝いに来てくれた人たちに、祝われる本人が「今日はありがとうございました」と挨拶をします。
しかし葬儀の主役は亡くなっているあけですから、挨拶をしようにもできません。だからこそ、代わって挨拶をするのが喪主の勤めでもあります。
喪主の役割とは、
- 葬儀の中心になってまとめ役をする
- 葬儀を主催する側の代表に立って挨拶をする
が中心になります。
もちろん自分はまとめ役だからといって椅子に座ってのんびりしているのではなく、段取りを組んで他の家族や手伝いに来てくれた人に指示を出し、葬儀場の人と詳細を詰めるなど、葬儀の柱として頑張ることになります。
喪主とは何?どんなことをするの?注意点は何?と考えた時には、まずは「喪主はいわば幹事」であり「主催側の代表でまとめ役」ということを意識してみてください。
そうすれば、喪主のこと、そして注意点について見えてくるものがあるのではないでしょうか。
第一の注意点!喪主の選び方とは

喪主は一般的に配偶者や長男がなることが多いです。
例えば、夫が亡くなった場合に妻が喪主を務めることは珍しいことではありません。
妻が亡くなった場合に夫が喪主を務めることも普通です。
ただし必ず配偶者でなければいけないという決まりはありません。
夫が亡くなった場合に妻が喪主を務めるのではなく、息子が喪主を務めることもあります。
息子がある程度の年齢であれば、父親が亡くなった時に母親よりも息子が喪主を務めることの方が多いかもしれません。
また、娘が喪主を務めてはいけないということもありませんので、喪主を選ぶ場合は「世間的に見て」ではなく、葬儀を主催する側において「誰をまとめ役にしたら上手く葬儀が回りそうか」ということに注意をする必要があります。
先ほどの例で、息子が三十歳を超えており父親の葬儀は息子が喪主としてするのがいいのではないかという話が出たとします。
しかし父親と母親、娘は地方都市の実家に住んでおり、息子は東京で仕事をしており、到着は葬儀のぎりぎりになるという話だったとします。
この場合、もちろん息子を喪主として立てることは選択肢の一つです。ぎりぎりに到着するからといって喪主をしてはいけないという決まりもありません。
ですが、喪主は葬儀の幹事でありまとめ役です。
葬儀はいざ葬儀開催となる前にたくさんの細かな準備事があります。
ぎりぎりに到着する人を喪主にしてしまうと、まとめ役として準備を進めることができませんよね。
ですから、こんな時は息子が適任という話になっても、あえて娘や母親が喪主として立つことも一つの方法です。
- 喪主は誰がしなければいけないという決まりはない
- ただ、一般的に配偶者や子供(特に長男)が立つことが多い
- 喪主は幹事でありまとめ役。まとめることが難しいなら別の人を立てることも検討
喪主である息子が到着しないから葬儀の準備がなかなか難しいということになってしまうと本末転倒です。
そうならないように、喪主は葬儀をしなければならないとなったら、真っ先に適任者を決めましょう。
代表を決めることで葬儀場との相談もスムーズに進みますし、決定権者として喪主がいることから、決めるのが難しいことも「喪主に一任しよう」という形で決めることができます。
喪主の務めとは?施主とは違うの?
また、喪主の仕事の範囲は特に決まっていません。
どうしても私生活の都合で細かいことまで手が回らないということであれば、時に分業をすることも重要です。
葬儀で「喪主」の他によく聞かれる名前として「施主」があります。
施主とは、主に集金や支払いなどのお金の計算を担当する役割を担う人のことです。
施主と喪主は兼業されることも多いのですが、分担してしまうのも一つの手です。
前述した事例で説明するなら、喪主はぎりぎりに到着する息子が担当し、施主は母親と娘で担当するという分担方式です。
そもそも喪主は「これを絶対にしなければいけない」という仕事上の決まりは特にありません。
唯一、絶対に葬儀中にすることになるのは「挨拶」「お別れの際の代表」など、主に表に出てすること、亡き人とのお別れとして誰か一人が代表でする時に喪主が代表になること、です。
集金などの裏の仕事は家族に分担してもらい、喪主だからといって全て背負い込まないように注意しましょう。
喪主は大切な役割ではありますが、葬儀は亡くなった人と参列者、そして喪主の家族を含めた皆で成功させることです。ですから、喪主だけが「全部やらなければ」ということはありません。
- 喪主だから挨拶や代表以外の裏方も全部担当するわけではない
- 適度に家族や親族に仕事を分担する
- 何かあったら都度、判断する
以上の点を注意しておけば喪主として全て背負う必要はありません。円滑に葬儀が進むように、特に裏方の仕事は分担しましょう。
最後に
自分が喪主になると、特に葬儀を経験したことのない人は「喪主だから」「自分がやらなければ」と全て背負い込んでしまうきらいがあります。
しかし喪主が全てをしなければいけないのではなく、喪主はあくまで幹事でありまとめ役です。
飲み会の幹事だって、飲み会の規模が大きくなれば同じ会社の部署の人に集金や場のセッティングなどを手伝ってもらいますよね。喪主も同じように考えて差し支えありません。
もし私生活が手一杯で、それでも喪主をしなければならないのなら、喪主としての第一の役目である「挨拶」を中心に、後は家族や親族に分担してしまいましょう。
最終的に葬儀がスムーズに進めばOK。
喪主になってもそう気負わず、「自分はこの葬儀の幹事である」という意識を持ってすれば、喪主という掴み難い立場を理解する早道になるはずです。